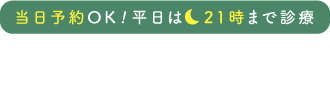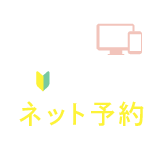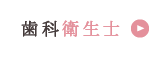みなさんは正しい歯の磨き方を知っていますか?
お口の中には常に菌が存在していて、食事をした時に糖が入っていると、その菌が糖を栄養としてプラーク(=歯垢)を作り出します。
そのプラークが、虫歯や歯周病の原因になってしまうのです。
それを落とすために、定期的に歯科医院でクリーニングすることも大切ですが、それより重要なのは毎日の歯磨き。
歯磨きによってプラークは落とすことができるのですが、適当に歯ブラシを動かせば綺麗に取れるものではありません。
プラークが付きやすい位置を理解して、そこの汚れを落とすための動かし方とブラシの当てる位置を意識して歯ブラシを動かさなければ、せっかく毎日歯を磨いているのに無意味になってしまうかも…
このように言うと難しいように聞こえていまいますが、コツを覚えてしまえばとっても簡単!
正しい歯の磨き方をマスターして、虫歯ゼロを目指しましょう!
まず磨き方を説明する前に、どこにプラークが付きやすいのかを理解しなければなりません。
そこから勉強していきましょう!
プラークが付きやすい場所は大まかに分けると3つあります。
それは…
- 歯と歯茎の境目
- 歯と歯の間
- 奥歯の噛み合わせの溝
この3箇所がプラークのつきやすい部分となります。
この3箇所はプラークのつきやすい部分でもあり、また歯ブラシを当てにくい、プラークを落としにくい部分でもあるので虫歯ができやすくなります。
虫歯ができたことのある方は、よく考えていただくと先ほど挙げた3つのどれかから出来てはないでしょうか?
では歯の表面にはなぜプラークがつかないのか?
なぜ虫歯になりにくいのでしょうか?
歯の表面は歯ブラシが当てやすいこともありますが、普段の生活でも汚れが落とせているのです。
例えば食事や飲み物を飲んでいる時でも物が当たることによって汚れが落ちたり、また唾液によっても汚れを落としたりすることができるのです。
唾液にはそのような自浄作用があったり、また口内細菌の増殖を抑える抗菌効果や、虫歯になる時は歯が脱灰(歯の表面が溶け出す)するのですが、それを修復したりしてくれる効果があります。
そのため、歯の表面や先端の方は食べ物や唾液が物理的に当たりやすいためプラークがつきにくく、虫歯にもなりにくくなるのです。
なので、歯の表面はそこまで意識して磨かなくても大丈夫なのです。
では実際にプラークがつきやすい部分はどのように磨けばいいのか、次で説明してきましょう。